2015年11月19日
勉強中です。論語学而第一です。
…

…
論語について勉強中です。
全部できてからアップしようと思ってましたが、
ちょっと思うところあって、勉強した部分のアップします
ちょっとだけです。
論語学而第一です。
〈智、向上心、学習の朋友、自己啓発と同志、有名に無らなくても学び続ける、
学芸の友、勉強仲間、音楽の友、同じ趣味仲間、リーダーのあり方、認められなくても〉
学而第一 001学而第一 の001
推薦
http://www.niigata-ogawaya.co.jp/rongo3/s-01-001.htm
http://kanbun.info/keibu/rongo0101.html
「子曰く、学びて時に之を習う、またよろこばしからずや。朋(とも)遠方より来たる有り、また楽しからずや。人知らずしてうらみず、また君子ならずや。」
・時に習う、、、復習するとか、繰り返し練習するとか書いてある。
・朋友、、、志を同じくする友とある
・説ばしい=よろこばしい、、、調べると、下記のサイトの説明が良さそう。
単なる喜ばしいと、意味が違うようです。
http://1st.geocities.jp/ica7ea/kanji/yorokobashi.html
・不慍=うらみず=いきどおらず=下記のサイトの説明が良さそう=腹を立てず
http://kanbun.info/keibu/rongo0101.html
、
学んで、時に復習する。ああ、そういうことだったのかと、感じ入る。
同志である朋友が、遠方より訪ねてくることがある。
なんと楽しいことでは無いか。
人に知られなくても認められなくても、腹を立て無い、
それでこそ君子(人格者)だ
、
女性のブログでは、男は資格や習い事などの勉強をしない人が多いと書いてあることが多い。
それが本当かどうかは知りませんが、どうでしょう。
私も、社会保険労務士やその他の勉強をしていた時、専門の学校には同志はいたけど、
職場や地域社会などでは、同じ勉強をしている人はいませんでした。
寂しいと、思うわけですなあ。
私は音楽が、思いっきり好きというわけで無いので、想像ですが、
バンドを組んで活動するほど音楽が好きな人は、なかなか同じくらい音楽が好きな人は、
周りにはいないんじゃ無いでしょうかね。
だから、勉強でも、趣味でも、同志や深い仲間というのは貴重で、
見つけたら、遠い所へでも会いに行ったりする。
それほど、同じ志を持つ朋友は大切なものです。
孔丘先生は、楽器の先生や学問の同志先生が訪ねてきたら、夜が明けるのが忘れるくらい、
夢中に話し込んだというでは無いですか。
、
論語の一番最初に、この、学問や向上心、啓発に関係する文章が出たというのは、
孔丘先生が、いかに学問好きか、向上心があったかを暗示していると思う。
同時に、論語を学ぶものも、繰り返し学ぶのであれば、この一番目の話こそ、重視して、
我らも向上心を持たねば、ならんと思うわけですなあ。
また、勉強にしても、音楽にしても、趣味にしても、仕事にしても、
認められないからいい加減にすると言うのでなく、
認められなくても一所懸命にすると言うことの大切さも言ってる気がする。
というより、認められなくても、楽しんで夢中になるというのがいいねえ。
〈仁と礼、孝悌、目上に反抗的を反省、親孝行と目上を敬うことは仁の第一歩、先輩をおろそかにしない事〉
学而第一 002学而第一 の002
推薦
http://www.niigata-ogawaya.co.jp/rongo3/s-01-002.htm
http://kanbun.info/keibu/rongo0102.html
有子曰く、その人となりや孝弟にして、上(かみ)を犯すを好む者はすくなし。上を犯すことを好まずして、乱をなすを好む者ものは未だ之、有らざるなり。君子は本(もと)を務む。本立ちて道生ず。孝弟なる者は、それ仁の本為(た)るか。
、
・上(かみ)を犯す=目上の人にさからう、楯突く
http://kanbun.info/keibu/rongo0102.html
・本為るか、、、辞書で「為(な)す」は、あるが、「為(た)る」は、無いような気がする。
「為(な)す」は、成る・成すで、そうなるとか、そうするとか、いう意味で、
「本為るか」とは、どういう意味やねん。多分、「根本を形作る=根本である」。
漢文説の「実践にその根本があった」は、実践としている。
新潟説は、「第一歩と云って良い」は、本=第一歩、為す=と言って良い、
つまり、◯◯と言って良い=形作る根本要素=第一歩と言って良い
新潟説
有子(孔子の弟子の有若(ゆうじゃく))云う、「その人柄が、親に孝行で兄に悌順(ていじゅん・従順)な性格であれば、好んで目上の人にたてつく者など、滅多にいないものだ。目上の人にたてつくことが嫌いな性格であって、それでいて社会の秩序を乱すことが好きだなどという者は、未だかつてあったためしがない。立派な人物は、まず根本をしっかりと押さえるものである。何事も根本が定まれば、道は自ずと開けるものだ。この親に孝行で目上に悌順であるということが、思いやりのある人づくりの第一歩と云って良いだろう」と。
漢文説
有ゆう先生がいわれた。家庭において、親には孝行であり、兄には従順であるような人物が、世間に出て長上に対して不遜であったためしはめったにない。長上に対して不遜でない人が、好んで社会国家の秩序をみだし、乱をおこしたというためしは絶対にないことである。古来、君子は何ごとにも根本を大切にし、まずそこに全精力を傾倒して来たものだが、それは、根本さえ把握すると、道はおのずからにしてひらけて行くものだからである。君子が到達した仁という至上の徳も、おそらく孝弟というような家庭道徳の忠実な実践にその根本があったのではあるまいか
早◯案
有子言う、家庭において、親には孝行であり、兄には従順であるような人物が、世間に出て目上に対して反抗的であったためしはない。目上に対して反抗的でない人が、社会の秩序をみだし、乱・犯罪・大事件・テロをおこしたというためしはない。君子(人格者)は何ごとにも根本を大切にし、まずそこに全精力を傾倒して来たものだ。根本さえ把握すると、道はおのずからにしてひらけて行くものだからである。仁という至上の徳も、おそらく孝弟というような家庭道徳の忠実な実践にその根本があったのではあるまいか
、
さて、とんでもない説を唱えます。
この章の仁について、有子が言ってるのであって、孔子が言っていない。
仁の中で、孝悌が一番大切という話、、、
これは、儒学が、専制政治や独裁に利用されてきた原因では無いかと思う。
親を大切にし、兄を大切にし、目上を敬うことは大切だ。
でも、それが仁の根本とはならないと思う。
仁の根本は、忠恕、「真心=嘘をつかない真実の心」と「思いやりや許す心」だと思う。
これは、今の中国人を見ていて強く思う。
親孝行を大切にしていて親に忠実な中国人であるが、
嘘だらけ、利己主義だらけ、思いやりや許す心が無い、そういう気がしてなりません。
中国人は、目上に従順で、悪いことでも一族のため、なんでもします。
上下関係を重視して、上の言うことなら、どんな悪いことでも、従います。
それって、真心なんですか?
それって、いいことなんですか?
だから、この章は、歴史に傷をつけた不道徳を残した章であると、そう思う。
、
もう一度言いますが、親や目上に従順であることは、大切です。
でも、それが仁の根本であるとは、とても思えません。
嘘を隠して目上に従順であることは、独裁や専制政治を許すことになります。
今の中国人の皆様、それでいいのですか?
孝悌の重要性を否定するものではありません。
家庭における道徳である孝悌、多少の間違いを含んでいても、
親や目上に従順であることは、小集団で、皆が幸せになるためには必要なこともあると、
認めます。
ただ、それ以上に、真心と思いやりが大事だと、そう言ってるだけです。
当然、中国の今の独裁政権に、賛成できるわけがありません。
日本だって、独裁に向かうのであれば、賛成できるわけがありません。
ただ、日本は、独裁ではありません。
第一次安倍政権時代に作られた憲法改悪案が、独裁に向かう臭いがするだけです。
案作成者たちは、独裁に向かうつもりかどうかは、断定でき出来ない。
ただ、独裁に向かうことが可能な文章であるだけです。
今の中国が現実に独裁状態であることとは大きな違いがあります。
ただ、国民は、自民党が独裁へ暴走しないように、注視し、時に声を上げる必要があるだけです。
そこで、早◯案の訂正をいたします。根本→第一歩。
、
早◯案、訂正
有子言う、家庭において、親には孝行であり、兄には従順であるような人物が、世間に出て目上に対して反抗的であったためしはない。目上に対して反抗的でない人が、社会の秩序をみだし、乱・犯罪・大事件・テロをおこしたというためしはない。君子(人格者)は何ごとにも第一歩を非常に大切にして来たものだ。第一歩さえ間違え無いと、道はおのずからにしてひらけて行くものだからである。仁という至上の徳に関しても、おそらく孝弟というような家庭道徳の忠実な実践が、重要な第一歩ではあるまいか
、
目上を敬う事について、一つの良い見本がある。宝塚歌劇の学校での話だ。
ここでも、独裁的な臭いがしないわけでは無いが、礼儀を守り、先輩をたてる事を、
徹底して学ぶという話を聞く。そこから、人間関係が生まれ、引き立てや、
仕事につながるとかあるという話だ。正しい礼儀は、人脈であり、
間違った無礼は、仕事を失う原因となる。
宝塚歌劇に限らず、ビジネスにおいても、ビジネスマナーは、大切だ。
目上を敬う事についてでした。
〈仁と礼、巧言令色、心の嘘、巧みな言葉やお世辞、愛想笑いや取り繕い、
ごますりヨイショ、孔丘先生の嫌いな事〉
学而第一 003学而第一 の003
推薦
http://www.niigata-ogawaya.co.jp/rongo3/s-01-003.htm
http://kanbun.info/keibu/rongo0103.html
子曰く、巧言令色(こうげんれいしょく)、鮮(すくな)し仁。
、
巧みな言葉・お世辞や、愛想笑い・媚びる表情の中に、仁は少ない。
、
仁は、「真心と思いやり」「人格の高さ」などですが、この場合、嘘で無い・真摯な心=真心という意味が強いと思う。しかし、「『人格の高さ』が少ない」という意味も、捨てがたい。
色=表情など(外見から分かること)。
、
「愛想がいい」というのは、笑顔を見せ心が純粋に見えることが多い。
相手に対して何の見返りも期待してい無いことが多い。真心があれば、奉仕の心。
真心が無ければ、愛想笑い・令色、ごまかし。上記の「愛想笑い」は、よく無い意味。
「媚びへつらう」というのは、必要以上に相手の機嫌を取ること。
いやな相手に対し、自分の心にうそをつきます。そのかわりに、何か見返りを期待します。
上下関係で下が上に媚びへつらう時に、よく使われる。上下関係で無くても使うこともある。
、
非常に、重要だと思う。
巧言や令色は、心の嘘だと思う。
仁の意味がわかっていないと、分からない。
〈毎日の反省、人のための忠義、友と信義、知ったかぶり、人のために行動すること〉
学而第一 004学而第一 の004
曾子(そうし)いわく、われ日にわが身を三省す。人の為に謀(はか)りて忠ならざるか、朋友と交わりて信ならざるか、習わざるを伝うるか。
、
曾先生は、毎日の日課として、三種類の反省をしているらしい。
大事なことだと思う。
・人のために行動する時に、真心から行動したか。真心(忠)も大事だし、人のために行動するということも大事ですね。忠=ふた心・裏表の無いこと、真心。『全力を尽くす』説も捨てがたい。つまり、人のために行動する時に全力を尽くしたか?
人のため行動するのに、真心が無いということがあるとしたら、「私心」のせいだと、
新潟の高野先生は言ってる。私心=利己主義・自分の利益を目的とすることですな。
つまり、高野先生は、「私心」が無かったかの反省が重要だと言っています。
なるほど。忠の意味が重要ですが、本当はどういう意味でしょうか。
「人の為に謀(はか)りて忠ならざるか」人のために行動して忠に背かなかったか、って。
忠の意味、難しいですね。
・友人との関係では、誠実であったか。信義に背かなかったか。
うーん、意外と、信=信用=嘘をつかない、で、「嘘をつかなかったか」の反省かも。
・習っていないことを伝えなかったか。知ったかぶりしなかったか。
「実践できるほど身についていないことを、人に教えなかったか」説は、厳しく考えすぎのような気がする。
、
〈政治、事業に真剣に向かう、節約の大切さ、税や徴収はいたわりを、労働させるに思いやりや時を考えて。集団の治め方。人にものを頼む時〉
学而第一 005学而第一 の005
子のたまわく、千乗(せんじょう)の国を道(おさむる・みちびく)に、事を敬して信、用を節して人を愛し、民を使うに時をもってす。
、
政治の話ですね、でも、家族運営や企業運営、すべての集団に役立てる話だと思う。
商売のコツも、ブラック企業防止も、家族の協力関係強化も、ここにあるね。
千乗の国=大国
・「事を敬して信」は、事業を行うのに一つ一つ丁寧にまじめに取り組んで信頼を得て。
敬して=「慎重に」説と「敬う=一つ一つ丁寧にまじめに」説、後者をとりました。
・「用を節して人を愛し」国の費用を節約して節税で国民の税負担を軽くすることで国民をいたわり
・「民を使うに時をもってす」=国民に労働を課するに、農期を避けるなど時と場合を考えて。
孔子の時代は、国民を農業以外にも、王宮や橋や洪水防止の防波堤などの土木建築に国民を使うことがあったのでしょうか?
今の日本では、例えば、裁判員制の裁判員は、義務ですね。スイスや韓国では、徴兵制で、一定期間軍隊で訓練を受ける義務があるとか。
、
子のたまわく、千乗(せんじょう)の国を道(おさむる・みちびく)に、事を敬して信、用を節して人を愛し、民を使うに時をもってす。
孔丘先生がおっしゃった。大国を統治するコツは、
・事業を行うのに一つ一つ丁寧にまじめに取り組んで信頼を得て、
・国の費用を節約して節税で国民の税負担を軽くすることで国民をいたわり
・国民に労働を課するに、農期を避けるなど時と場合を考えて。
行うことだ。
、
これは、すべての集団運営に当てはまることでは無いでしょうか。
リーダーの仕事に対しては、まじめに取り組み、
費用節約・仕事効率化などの採算性と、お金負担する人へのいたわりを考え、
労働負担する人に対しても、時と場合を考えて、思いやりをかけることですね。
先頭に立つ人の心得と、お金を負担する人・労働を負担する人両方への思いやりを。
、
また、人にものを頼む時も、相手への思いやりがあれば、時と場合を考えて、
頼む内容も頼む時期も慎重にできるでしょうと、先生はおっしゃってるのだと思う。。
、
用を節して人を愛し、、、国立競技場の高額予算を思い出しますね。複数の誰かがボロ儲けしようとしたんでしょうなあ。やっぱり、道徳的なリーダーは、節約を考えるってことです。
中小企業の悪社長もぜいたくな人がいますね。
「売り家と唐様で書く三代目」洒落た文字で『売り家』と書いてあるので道楽息子と分かる。
テレビでは、お金持ちを見せつける芸能人は多く、お金が全てという風潮があるが、昔から何代も続いている信用重視の老舗は、適度なお金の使い方しかしない、、、と、思うんだけどなあ。
、
少なくとも、バカスカお金を使いまくって、見せつけまくっているひとは、嫌われる。
人の気持ちを考え、思いやりを重視したら、貧乏な人へのいたわりもある。
、
追加。節税と税負担を軽くすること、、、今の自民党さん、孔丘先生が怒ってますよ。
国民を使う、、、派遣法や労働基準法の改悪、やめてええええ。
、
〈弟子(ていし=若者)のあり方、親孝行、従順、信用信頼誠実言行一致、人格者に親しみ見本に、ひろく衆を愛し〉
学而第一 006学而第一 の006
推薦
http://www.niigata-ogawaya.co.jp/rongo3/s-01-006.htm
http://kanbun.info/keibu/rongo0106.html
、
子曰く、弟子(ていし=若者)入りて(家庭で)は則ち孝、出でて(社会に出て)は則ち弟(年長者につかえて従順)、謹しみて信、汎く衆を愛して仁(=仁者)に親しみ、行ないて余力有れば、則ち以て文を学べ。
、
子曰く、若者よ、家庭では孝行し、社会に出たら年長者につかえて従順を心がけ、慎み深く誠実(信、嘘をつかない)にし、ひろくたくさんのひとを愛して、徳の高い人格者に親しみ見本とせよ。これらのことを行ない、余力が有れば、はじめて学問・古典を学べ。
、
・行ないて、、、「人格者の行動を見本として行動し」説と、「今まで言ったことを全部、行って」説がある気がする。全部した方がいいのでしょうなあ。
・文、、、学問。詩・書・礼・楽
・信、、、新潟高野先生は、「言行一致」と言っている。信=誠実に=裏表なく=言行一致、と、言えなくも無いが、普通に「信頼を大切に」とか、「誠実に」の方が自然だと思う。
、
甘やかされて育ったり、親に道具のように扱われてたりすると、子供は大きくなった時に反抗的になるのかもしれない。元教師で教育評論家の尾木ママ、尾木先生は、子供の反抗期は、親から独立する準備と言います。確かに、そういう面もありますが、反抗的なだけで終わると、大人の責任や辛さを知らずに、人のせいにして不幸になる気がします。
親から独立する準備として、心の壁を乗り越えるため、親の言いなりになる状態を抜けることも大切ですが、それ以前の幼い時期は、親に従い、人格者から学ぶことは非常に大切です。
また、親から独立しても、若い間は、目上をたて年長者から学び続けるべきでしょう。
、
新潟高野先生のおっしゃるように、学問だけの人間になるな道徳を行動して余裕があれば学問せよと、いうことも大切だ。
また、キリスト教の「隣人を愛せよ」と「ひろく衆を愛せよ」を比較しているのは面白い。「愛」の意味が、孔子の時代はどういう意味だったのかわからないので、必ずしも、キリスト教と比較はできないとは思うが、話題としては面白い。
、
〈よく学びよく働き親孝行で誠実ならば、人は、ほっておかない。ベストを尽くせ、力の出し惜しみするな。どんな人が雇われやすいか、求められるか〉
学而第一 007学而第一 の007
推薦
http://www.niigata-ogawaya.co.jp/rongo3/s-01-007.htm
http://kanbun.info/keibu/rongo0107.html
子夏曰く、賢を賢として色を易(か)え、父母に事(つか)えて能く其の力を竭(つく)し、君に事えて能くその身を致し、朋友と交わるに言いて信有らば、未だ学ばずというといえども、吾は必らず之を学びたりと謂わん。
、
賢人を賢人として見て態度を正し、父母につかえて力をつくし、主人につかえて能力を全力でこたえ、友人と交わる時は誠実ならば、まだ学問を学んでいないと言っても、この人は(道、つまり道徳を)よく学んでいる人とみなす。
、
新潟の高野先生は、こう書いています。
「人は与えられた環境・置かれた立場でベストを尽くせば、道は自ずから開かれる、 世間が放っておかない、ということを云いたかったのでしょう。力の出し惜しみをする人は、 いつの時代でも認めてもらえないということですね。」
なるほど、そういうことか。こういう人なら、社長も、「雇いたい」と言うのでしょう。
、
〈君子・リーダーは重々しく威厳、頑固になるな、ひろく学ぶことで頑固で無くなる、尊敬できない人を友人とすべきか、過ちを改めることを恥ずかしがるな〉
学而第一 008学而第一 の008
推薦
http://www.niigata-ogawaya.co.jp/rongo3/s-01-008.htm
http://kanbun.info/keibu/rongo0108.html
子曰く、君子重からざれば則ち威あらず。学べば則ち固ならず。忠信を主とし、己に如かざる者を友とすること無かれ。過まちては則ち改たむるに憚(はば)かること勿(な)かれ。
、
君子・リーダーは重々しく無ければ権威が保てない(軽々しいと軽蔑される)。ひろく学べば、頑固・かたくなに、ならない。まごころと信義を中心とし、人格が自分より劣る者を友とすることの無いように。過(あやま)ちを改めることを恥ずかしがるな。
、
全体の文章につながりがあるのか無いのか、分かりにくい。「忠信を主とし」と「己に如かざる、、、」の間に「、」の説と「。」の説が両方あり。つまり、忠信が、己に如かざる、、ともに関連した対話なのか、別々の対話なのか、実はよくわからない。
、
新潟高野先生は、「、」で区切り、「忠信を主とし、己に如かざる、、、友と、、、。」としている。
、
バラバラのいろんな話を付け足したようにも見える。
なぜ、こんなに、バラバラに見えるのだろう。
、
単純に、別々の文章だとわりきっても、いい教訓ではある。
・学べば則ち固ならず、、、難しいなあ。
頑固と言えば、沖縄の知事と政府の基地問題を、思い出す。移設反対の知事とその賛同者は、頑固な気がするが、彼らは彼らで、沖縄の昔からの歴史を考えた上で主張しているのだろう。昔、中国と江戸時代の薩摩などとの間で、苦しんでいた過去、中国よりも日本側の方からの仕打ちの方が、ひどい場面もあったのだろう。実際、第二次世界大戦での沖縄戦や、日本帝国軍からの住民への仕打ちは許せないという人もいるのだろうと思う。そういう意味で、沖縄の人々の気持ちも考えてあげ、同情してあげる必要はある。
しかし、中国の周りの国に対する独裁的な圧力の現実も見る必要がある。沖縄の人々は、そういうことを本当に学んでいるのだろうか。中国の周りの国・内部の少数民族へのひどい仕打ち、嘘で塗り固めた甘い接近方法。本当に、学んでいるのだろうか?。
あの、沖縄の知事は、中国から、お金を貰っていたり、名誉を与えられていたり、ハニートラップの女性の甘い誘惑で中国に味方するように仕向けられていないのだろうか?
どう考えても、中国の恐ろしさ、独裁的な圧力、自分の国民をも不幸にしていく思想教育や報道規制のものすごさ。そういうことを、沖縄の人々は、本当に学んでいるのだろうか?
頑固な反対派の人たち。
一方、政府側も、頑固である。なぜ、沖縄の人々の気持ちも考えてあげ無いのか、沖縄の昔からの歴史をちゃんと学んだのだろうか?そして、日本帝国軍の独裁の歴史をちゃんと学んだのだろうか?、過去を「済んだことは、もう考える必要は無い」と、切り捨てるのだろうか?
あるいは、人間の心理というものを、ちゃんと学んだのだろうか?今の安倍政権には、独裁のにおいがする。沖縄の人々を、説得するためには、もっと、思いやりを持って、でも、中国の現実をちゃんと教えていかねばならないと思う。情熱を持って、真剣に、日本のため沖縄の人々が、中国に独裁されることの無いように、伝えていく必要があると思う。
しかし、日本政府側が、独裁的な考えでいるから、説得できないのではないだろうか?。
私は、そう思う。
学べば則ち固ならず、沖縄の人々も、政府側も、学べば、頑固で無くなることができると思う。
そして、
過まちては則ち改たむるに憚(はば)かること勿(な)かれ。
、
・己に如かざる者を友とすること無かれ、、、
単純に読めば、自分より劣るものを友とするな、、、ですが。
「人格的に劣るものを」と、読み替えたり「知徳の劣るものを」と読み替えたり、
あるいは、前の文の「忠信を主とし」と関連付けて、「まごころの無い劣るものを」としたり、いろんな説がある。
今の中国人であれば「能力が劣る人を友人とするな」と、訳すかもしれない。
それは違うだろうと、考えるのであれば、前の文の「忠信を主とし」と関連するということで、説明できる。孔丘先生の生き方全体を考えれば、その方が素直で自然だ。
で、
「忠信を主とし、己に如かざる者を友とすること無かれ。」をセットと考えて、
まごころと信義を中心とし、人格が自分より劣る者を友とすることの無いように。
、
「人格が劣るもの」とは、「能力が劣るもの」のことでは無い。したがって、能力が自分より高くても、能力が自分より低くても、人格的に同じか優れている人であれば、友人にした方がいい。人格的に優れているとは、まごころや思いやりが有り、信用できる、利己的で無い、などのことであり、能力が優れているということでは無い。
、
この解釈は、新潟の高野先生も、おっしゃる通り、論語全体の見方に由来し、仁を一番重視する見方であると言える。そして、私も、その見方を取り、また、
http://kanbun.info/keibu/rongo0108.html には、
宮崎市定さん(論語の新研究)も、下村湖人(1884~1955)も、「能力が劣るものを友とするな」という解釈を取らないことが書かれている。
、
子曰く、君子重からざれば則ち威あらず。学べば則ち固ならず。忠信を主とし、己に如かざる者を友とすること無かれ。過まちては則ち改たむるに憚(はば)かること勿(な)かれ。
の
A「過まちては則ち改たむるに憚(はば)かること勿(な)かれ。」が、B「忠信を主とし、己に如かざる者を友とすること無かれ。」と、関連しているのか、いないのか、どちらとも取れる。また、どちらでも、いい教訓になる。
過ちをあらゆる過ちとすると、AB関連していないという説明になるし、
過ちを友人選択の過ちとすると、AB関連しているという説明になる。
友人選択に限定するという説明を取る人はいないだろうけど。
、
〈ご先祖を敬う、親の葬儀を丁重に、ご先祖を敬う儀式を心を込めて〉
学而第一 009学而第一 の009
推薦
http://www.niigata-ogawaya.co.jp/rongo3/s-01-009.htm
http://kanbun.info/keibu/rongo0109.html
曾子曰く、終を慎しみ遠きを追えば、民の徳厚きに帰す。
、
曾参(そうしん)先生がおっしゃった。親の葬儀を丁重に行い、ご先祖の祭りを怠らない習慣がひろく行き渡っていれば、民衆の徳は厚い社会になる。
人生の終わりを慎み、遠きご先祖を追うとは、そういうことで、徳を厚くすることに直結する。
、
新潟の高野先生は、お墓参りの習慣は、儒教から来ていて、元々の仏教にはなかったことを指摘している。儒教では、目上を敬い、ご先祖を敬うことを重視している。
ご先祖を敬うことで、現に生きている目上の方を敬う心も養われていくということだろうと思う。孔丘先生は、祭り・儀式が無くなることを心配されているが、その心が重要だということだと思う。目上を敬うことが、形だけにならず、心から敬うためにも、ご先祖を敬う儀式が重要だということだろう。
、
〈孔子の性格と政治を聞かれることについて、温(温厚)・良(善良)・恭(恭順)・倹(倹素)・譲(謙譲)、役職よりも理想〉
学而第一 010学而第一 の010
推薦
http://www.niigata-ogawaya.co.jp/rongo3/s-01-010.htm
http://kanbun.info/keibu/rongo0110.html
子禽(しきん)、子貢(しこう)に問いて曰く、夫子(ふうし)の是の邦(くに)に至るや、必らず其の政(まつりごと)を聞く。之を求めたるか、抑(そもそも)之を与えたるか。子貢曰く、夫子は温・良・恭・倹・譲(じょう)、以て之を得たり。夫子ふの之を求むるや、其れ諸(こ)れ人の之を求むると異(こと)なるか。
、
子禽(しきん)が、兄弟子の子貢(しこう)に問うた。
孔丘先生は各地の国に(どこの国でも)到着すると、必ず政治の話に関係される。これは、先生から求められるのでしょうか、それとも国の君主側から相談されるのでしょうか?
子貢答えて言った。
孔丘先生は、温・良・恭・倹・譲(じょう)なので、自然にそうなるのでしょう。
先生から、政治の話を求めることもあるが、他の人の求め方と違うのでしょう。
、
最後の行について
漢文説、、、下村湖人説、先生は徳を重視するので他の人の求め方と目的が違い、官位を求めるようなことはしないが、自然に政治の話にまで至るのでしょう。
新潟説、、、先生の方から話しを持ち掛けることもあるが、それは他の人がやるような自己PRとは違っている
、
温・良・恭・倹・譲(じょう)
・温=温厚、おだやか、おだやか
・良=善良、素直で良心的、素直
・恭=恭順、慎み深く丁寧、うやうやしさ
・倹=倹素、質素倹約、つつましやかさ
・譲=謙譲、控え目で 遜る、ひかえめで謙遜
、
暗に、謙譲や質素倹約、温厚、善良、うやうやしさの大切さを言っていて、
理想の人物像はこれだということを、言っていると思う。
下村湖人の説は、飛躍しすぎているが、孔子が、出世や官位よりも、徳治政治を目指していることは本当なので、あながち嘘では無い気がする。
新潟説は、うまいこと言うなあと思う。現代風。自己PR重視の現代に、そんなこと(自己PR・出世や肩書・お金)よりも思いやり重視の理想政治・理想ビジネス経営・理想集団経営の方が大事ですよって、言ってる。
、
その上で、孔子の性格、
質素倹約が、お金重視に疑問を呈し
温厚や恭順、謙譲が、自己主張に疑問を呈し
善良・素直が、反抗や批判ありきに
疑問を呈している。
現代のお金へのがめつさや、自己主張や、なんでも批判し反抗することに、
私も、疑問を感じるものであります。
2500年前と同じだなあ、がめつい人や自己主張や自分の出世の為なんでも批判的な人は昔も今も目立つ存在ですもんね。でも、彼らが、幸福な社会を実現するために進んでいるとは思えない(彼らは、自分の利益・出世重視で、周りに不幸を振りまいている)。
、
〈孔子の親孝行に対する考え方、親の死後三年は道を変えない、志を観る、行いを観る〉
学而第一 011学而第一 の011
推薦
http://www.niigata-ogawaya.co.jp/rongo3/s-01-011.htm
http://kanbun.info/keibu/rongo0111.html
子曰く、父在(いま)せば、その志しを観、父没すればその行いを観る。三年父の道を改むること無きは、孝と謂(い)う可(べ)し。
、
二説ある。「観る」の主語が、1子供の説と2先生などの観察者説
、
1「観る」の主語が、子供である説、下村湖人、新潟の高野先生、
志・行=父親のもの、観る=主語が子供
(親孝行な人になるために)
父親が存命中はその父の志・お気持ちを見て従い
父親が没したら父親の行いの後を見てしきたりなど継承し
三年(丸二年とちょっと)は、道・しきたり・家庭の生活習慣を改めない人は、
親孝行な人であると言える。
2「観る」の主語が、「先生」などの観察者説、観察者が子供の志・行を観る
http://lunyu.lightswitch.jp/?eid=2 論語ガイド
(その人が親孝行な人かどうかは)
父親が生きているうちは、その人の志で評価、観るべきで
父親の死後は、その人の行為で評価、観るべきだ。
父親の死後3年間、父親のやり方を変えなければ
親孝行な人間である
私は、論語ガイドの説が正しいと思う。
どちらにしても、この文章だけでは、孔丘先生が、何を言いたいのか、
よく分からない。うーん。
観察者が主語である説を取る理由は、
志=親孝行の意思のある本人の志、親に従おうとしているか、とし、
行=親孝行になっている本人の行い、死んだ親と同じ行動か、とすれば、
それを見て親孝行な人だと分かるから。それを三年続けよ、というのは、両方の説で共通。
もう一つの問題として、「道」の意味である。
国王や政治家、ビジネス継承や商売の代々続いている家などでは、
「道」は、よくわかる。しかし、一般家庭において、道とは、どういう意味だろう。
漢文説、下村湖人では、家庭の生活習慣と言っているが、はたしてそういう意味だろうか?
おおいに疑問である。
ただ、こう考えると、納得がいく。
つまり、儒学を宗教的にまで代々継承している家があるとしたら。
故人の弔い方に昔からのしきたりを守り、親・子・孫などの上下関係の礼儀作法に儒学を宗教的にまで行動し続けている家であれば、「道」は、その儒学の道だ。
多分、そういうことだろう。代々、儒教を、生活の隅々まで習慣化し、その中で、親孝行な人かどうかは、この章の説明によると、、、。
孔丘先生は、礼の先生であり、冠婚葬祭のしきたりの先生である。
時代は、そういう礼儀を大切にした時代であり、礼儀をおろそかにする人もいたという時代だと思う。だから、親孝行な人かどうかの先生の教えがあったのだろう。
、
〈有子、礼の運用、和をもって貴し、和・仲良しの行き過ぎで礼儀を忘れるな
親しき中にも礼儀あり〉
学而第一 012学而第一 の012
推薦
http://www.niigata-ogawaya.co.jp/rongo3/s-01-012.htm
http://kanbun.info/keibu/rongo0112.html
、
有子曰く、礼の和を用(もっ)て貴(たっ)としと為すは、先王(せんのう)の道も斯(こ)れを美と為す。小大 之に由れば、行われざる所あり。和を知りて和すれども、礼を以て之を節せざれば、亦(また)行うべからざるなり。
、
聖徳太子、十七条憲法、和をもって尊しとなす、の、もと
、
有先生が言った。礼の運用には和(調和)が大切である。過去の王も、調和を美徳とした。
しかし、小さなことも大きなことも全てが全て調和重視思考によれば、礼・礼儀が行われなくなることがある。和を知って和を行えども、礼によってこれ(和)を節制しないと、礼は行われなくなるものである。
、
早◯やわらか説(大学時代のサークル活動での会話)、、、礼儀は、調和・仲良しの心、中身を重視し大切だと考えている。しかし、すべて和、中身を重視するばかりで(外見をおろそかにするので)あれば、礼、ルール、規制が行われなくなる。和の重要性を知り調和・仲良しを行っても、礼・ルール・規制・暗黙の了解などで規制、節制しないと調和・仲良しは続かない。
(仲良し重視になりすぎると、「堅苦しい礼儀、言葉遣いはやめよう」となりがちである)
仲良し仲良しばかりで、言葉遣いなどの礼儀も無く、甘え合い、男女関係も乱れれば、仲良しに傷がつく(知らぬ間に心を傷付けてしまう)。長く仲良しを続けるためには節度や上下関係(先輩・後輩)などの秩序、礼儀作法は、必要である。
、
「行われざる所あり」や「行うべからざるなり」の主語が分からない。「礼」が主語と考えたが、それでいいのだろうか?
、
新潟説も下村湖人説も論語ガイドも、しっくり来ないので、勝手に考えましたが、
正しいかどうかは分からない。
、
〈有子、信・義・礼、うやうやしさ・丁寧さと礼、貴重な親しさと貴重でない親しさ〉
学而第一 013学而第一 の013
推薦
http://www.niigata-ogawaya.co.jp/rongo3/s-01-013.htm
http://kanbun.info/keibu/rongo0113.html
有子曰く、信、義に近ければ、言(げん)復(ふ)むべきなり。恭、礼に近ければ、恥辱に遠ざかる。因(よる)こと、其の親(しん)を失わざれば、また宗(そう)とすべきなり。〔宗(たっと)ぶべきなり。〕
有子曰。信近於義。言可復也。恭近於禮。遠恥辱也。因不失其親。亦可宗也。
・後半の意味が、どの説明も納得がいかない
・因=頼りにすることとあるが、本当だろうか?日本の漢字の意味としては、原因の因、事のもととなるとか、〇〇によるとかいう意味だ。
因不失其親。亦可宗也。
「その親しさを失わないことにより(因り)尊いものとなることができる」では、ダメなのか?
後半について
論語ガイド説、、、「人選を間違わなければその人に頼れる」どういうこっちゃ
下村湖人説、、、「人にたよる時に、たよるべき人物の選定を誤っていなければ、生涯その人を尊敬していけるものだ」因の意味を頼りにすることとしているのが、どうしても納得がいかない。
新潟説、、、「婚姻によってできた新しい親類とも、親しく交際できるようになれたら、まずまず合格と云った ところだね」因=婚姻としている。これも納得いかない。
前半は、新潟説が納得できる
前半
新潟説、、、「一旦約束したことが道義(社会正義)に叶っているならば、その通り実行して 良いだろう。うやうやしさがちゃんと礼に叶っていれば、人から馬鹿にされることもないだろう。」
、
早◯は、こう考える。有先生は、前の章もそうだが、礼を大事にしていると思うので。
、
有子曰く、信、義に近ければ、言(げん)復(ふ)むべきなり。恭、礼に近ければ、恥辱に遠ざかる。因(よる)こと、其の親(しん)を失わざれば、また宗(そう)とすべきなり。〔宗(たっと)ぶべきなり。〕
有子曰。信近於義。言可復也。恭近於禮。遠恥辱也。因不失其親。亦可宗也。
、
有先生が言った。信(約束を守ること・公約を果たすこと)が、義(正義・道義・社会正義)にかなっていれば、その言葉どおり、ふみ行うべきだ。うやうやしさ・丁寧さが、礼にかなって、嫌味がなく卑屈で無いならば、馬鹿にされたり軽蔑されない。
その親しさを失わないことにより(因り)その人間関係・選挙などの人選は、尊いものとなることができる。
、
前半と後半は、関連性があると思う。そうであるならば、信・義・礼に関連することで統一すべきだと思うので、このような意味であるという提案にした。
どちらにしても、前半は似ているものの、後半の説明が、ネットの三つの説明のどれも納得がいかないものであります。
「その人間関係・選挙などの人選は」を、挿入した理由は、何が尊いかを考えて、信・義・礼につながる主語は、これだと思い、挿入いたしました。
、
この文章をみると、どうしても、選挙の公約を守らない政治家や、利己的えこひいきな公約を掲げる政治家を思い出す。信が義にかなうこと、政治では大事だ。ペコペコ卑屈に選挙前だけ頭を下げまくる政治家も信用できない。そんな政治家と親しくなっても、全然尊いとは言えないが、信義あり礼にかなう政治家と親しくなって、良い政治のための意見が伝わるようになれば、それはそれは貴重なことだ。そう、思う。政治家との関わりだけでなく、すべての人間関係で信義も礼も大切。その上で、親しければ、宝なり。
、
新潟の高野先生の逆説は、いい発想。私も考えてみるか、、、
「約束をしても道義に反すると気づいたら行うべきでない(同じ)。
うやうやしく見えても巧言令色で、卑屈に見えたら、馬鹿にされるだろう。
そんな見せかけの親しさは、尊くない。」かな
、
〈孔子、飽食を避けよ、安逸を避けよ、大事な行動は迅速に、口を軽々しくするな、道義に沿う人に教わる、学を好む・向上心〉
学而第一 014学而第一 の014
推薦
http://www.niigata-ogawaya.co.jp/rongo3/s-01-014.htm
http://kanbun.info/keibu/rongo0114.html
、
子曰わく、君子は食 飽(あく)を求むること無く、居(きょ)安きを求むること無し。事に敏(びん)にして言に慎しみ、有道(ゆうどう)に就(つ)きて正す。学を好むと謂(い)うべきのみ。
、
この説明は、3説とも、だいたい同じだ。わかりやすいのは新潟説なので、
引用させていただく。
、
新潟説
孔子云う、「人の上に立つ者は、旨いものを腹一杯食べて、快適な家に住みたいなどという ことを真っ先に考えてはならん。人として為さねばならぬ事を最優先し、言葉を慎む。有徳の人物に師事して教えを受け、自分の至らぬ所を矯正して行く。こういう人こそ、真に学問好きと云って良いだろう」と。
あえて言えば、2行目の「人として」を、削除したほうがいいと思う。普通に、「為さねばならぬことを優先し迅速に」のほうがいいと思う。
、
孔丘先生らしい文章だと思う。
食より住居より、学を優先する人と、親しくなりたいのが孔丘先生だと思う。
では、なぜ、食より住居より学を優先するのか、それは、仁であり思いやりのある社会を作っていくために、学ぶ力を使おうとしたのだと思う。
食を全く食べないことを言ってるのでなく、住居が全くないことを言ってるのでなく、食べ過ぎや安楽しすぎを問題としているのだと思う。
学を優先し、理想社会を作るために自分を向上させること、それがいいと言っている。
特に、君子は。
、
〈孔子と子貢、へつらいとおごりダメよ、道を楽しみ富て礼を好む、共に詩を語る、共に道を語る〉
学而第一 015学而第一 の015
推薦
http://www.niigata-ogawaya.co.jp/rongo3/s-01-015.htm
http://kanbun.info/keibu/rongo0115.html
、
子貢(しこう)曰く、貧しくして諂(へつら)うこと無く、富みて驕(おご)ること無きは何如(いかん)。子曰く、可なり。いまだ貧しくして道を楽しみ、富て礼を好む者には若(し)かざるなり。子貢曰く、詩に云う、切するが如く磋(さ)するが如く、琢(たく)するが如く磨するが如しと(切磋琢磨)。それ、これを之(これ)謂(い)うか。子曰く、賜(し)や、始めて与(とも)に詩を言うべきのみ。諸(これ)に往(おう)を告げて来(らい)を知る者なり。
子貢が言った。「貧しくても、へつらうこと無く、お金持ちになってもおごらない人は、先生どうでしょうか?(立派ではないでしょうか?)」
先生曰く、「まあまあですね。でも、貧しくても道徳・道を楽しみ、お金持ちになってもおごらないどころか、礼儀や礼の心(で自分に厳しいこと)を好み続ける者には、かなわないだろうね。」
子貢が言った、「詩経に、切るごとく、磋(す)るごとく、琢(う)つごとく、磨(みが)くがごとく、たゆみなく、道にはげまん(漢文体系説)(切するが如く磋(さ)するが如く、琢(たく)するが如く磨するが如しと(切磋琢磨))とあります。このことですか?」
先生曰く、「そうです、それでこそ(=始)、賜(し)(=子貢)であるよ。共に詩を語ることができる。(言葉が)行けば戻り、打てば響く、一を聞いて次が分かる者であるよ。」
へつらう=コトバンクでは、目上・上位の者におもねたり、お世辞を言ったり、追従(ついしょう)したりするとあります。
web漢文体系では、諂(へつらう)=卑屈(ひくつ)になって憐れみを乞う。とあります。
http://kanbun.info/keibu/rongo0115.html
でも、卑屈の意味は、「自分をいやしめて服従・妥協しようとする、いくじのない態度。」と、あり、微妙に違います。(どうせ、所詮、もともと、、、、)
コトバンクのへつらう=気に入られようとする時
漢文体系の諂う=卑屈=自分をいじめて同情を買おうとしている。
話はそれるが、知っておいたほうがいい類似語、、、
「へつらう(上に)」に似ているが違う言葉として「媚(こ)びる(下に)」がある。
媚びる=部下(や、同僚)に気に入られようとしたり、機嫌をとったりする(下心がある)。また、女性が性的に気に入られようとすることも媚びるというコトがある。
「謙虚」と「卑屈」の違いは、批判から逃げているかどうかという説がある。
http://kemonomichiwoikou.blog.jp/archives/26255764.html
卑屈、、、弱さ欠点批判から逃げる態度、成長することが無い
謙虚、、、逃げていないので、向上心・吸収力でもある。謙虚な人は「批判・叱られたこと・売れないこと・失敗など・自分より優れている人」から学ぼうとする。
また、傲慢・おごり・偉そうな態度が、人に嫌な思いを与えることを知っていて、「人に嫌な思いを与えないように思いやりを持って偉そうにせずに人に接すること」も「謙虚」というのだと思う。
道・・・道徳行動。道徳を行動し続け習慣化して進み続けることだと思う。それを楽しむことですね。
漢文体系より。切 … 骨の加工法。磋 … 象牙の加工法。琢 … 玉ぎょくの加工法。磨 … 石の加工法。切磋琢磨、、、学問・道徳に、励みに励むこと。また、仲間同士互いに励まし合って向上すること。
心理学の専制的リーダーと民主的リーダーの話を、思い出す。どちらが、部下のやる気を引き出すか?民主的リーダーである。ただ、学而第一の12番目、「和を知りて和すれども、礼を以て之を節せざれば、亦(また)行うべからざるなり。」民主主義(和)も大切だが、秩序、礼の心=厳しさも大切であることを忘れてはならない。
この章は、「貧しくてもへつらわない、金持ちでも驕らない」→「貧しくても道を楽しみ、金持ちになっても自分に厳しく礼を好む」→「切磋琢磨で道徳を向上する」と展開し、弟子が詩経を引用した事で、師が共に語り合える事を喜んだという話です。
堅苦しい話なのに、孔子が喜んでいる。向上心と共に学べ語らう喜びが伝わってくる。
〈自分が有名になれない事、人に認めてもらえない事に悩むより、自分が人の事を知らない事、認めていない事を悩み、反省せよ〉
学而第一 016学而第一 の016
推薦
http://www.niigata-ogawaya.co.jp/rongo3/s-01-016.htm
http://kanbun.info/keibu/rongo0116.html
子曰く、人の己を知らざるを患(うれ)えず。人を知らざるを患うるなり。
自分が有名になれない事、人に認めてもらえない事に悩むより、自分が人の事を知らない事、認めていない事を悩み、反省せよ
患(うれ)う=悩みわずらう事、心配する事。心配→反省
コトバンクより
https://kotobank.jp/word/%E7%85%A9%E3%81%86%E3%83%BB%E6%82%A3%E3%81%86-415638
https://kotobank.jp/word/煩う・患う-415638
煩う・患う わずらう
大辞林 第三版の解説
わずらう【煩う・患う】
①心の中で悩む。苦しむ。心配する。 《煩》 「思い-・う」
②病気になる。 《患》 「長く-・う」 「胸を-・う」
③障害にあって苦しむ。難渋する。
④動詞の連用形の下に付いて,…するのに困る,の意を表す。
人の目を気にするより、自分から人を認める努力が十分であったか?
…

図については
http://hayamarukouhuku.osakazine.net/e542015.html
…
サイトマップ↓
http://hayamarukouhuku.osakazine.net/sitemap.html
…
論語について推薦サイト
⒈新潟の「論語に学ぶ会」高野大造先生
http://www.niigata-ogawaya.co.jp/rongo3/index.htm
⒉Web漢文体系 の中の、論語のページ
http://kanbun.info/keibu/rongo00.html
⒊論語(ろんご)ガイド
http://lunyu.lightswitch.jp/
、
過去記事『道徳、子供達への道徳教育、大人へは?まとめ、目次的。新学習指導要領』
http://hayamarukouhuku.osakazine.net/e567121.html
、
『このブログ内のトマ・ピケティさん『21世紀の資本』記事の超短くまとめ』
http://hayamarukouhuku.osakazine.net/e567723.html
…
サイトマップ↓
http://hayamarukouhuku.osakazine.net/sitemap.html
みなさんのコメント、メール、お待ちしています。
メールは、パソコンは左の二つ目の四角枠の中、スマホはプロフィールのしたの方、の「オーナーへメール」へどうぞ
記事にしてほしいことなど、質問など、なんでもどうぞ。
また、お名前は、ハンドルネーム(ネット上の自称のあだ名・愛称)で、どうぞ。
▼オーナーへメールは、
2014/05/16 重要 オーナーへメール について
http://hayamarukouhuku.osakazine.net/e538923.html
http://hayamarukouhuku.osakazine.net/profile.html
…
…
…
このブログ内人気記事上位100 古くてごめん
http://hayamarukouhuku.osakazine.net/e553066.html
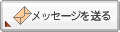
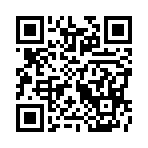
 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン













